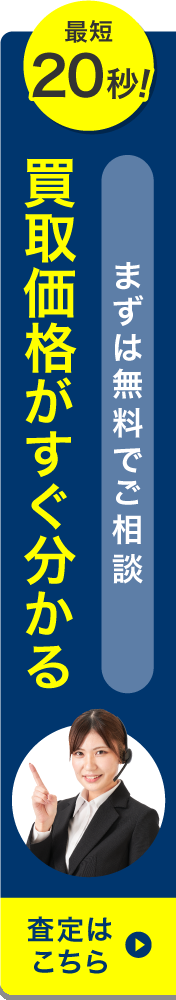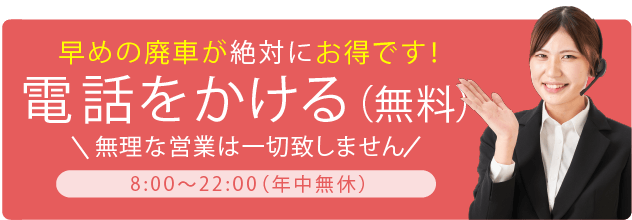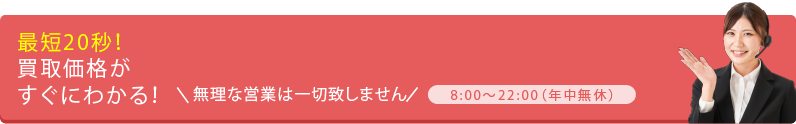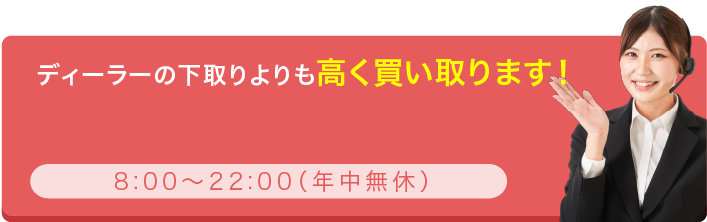車を購入して数年が経過すると、気になってくるのが「この車はあとどれくらいの期間まで動くんだろう」という車の寿命です。
ある人は何十年も同じ車に乗っているのに、ある人の場合はほんの数年で不動車になってしまい廃車にしたという例もあります。
果たして、車の寿命と関わりのある年数・走行距離の平均値は、具体的にどれくらいなのでしょうか。今回は、車の寿命に関する情報、廃車の方法、寿命を伸ばす秘訣などを詳しく紹介しましょう。
もし、寿命を迎えてしまった車の廃車にお困りの時は、ぜひハイシャルをご利用ください。
どんな車でも0円以上の買取保証。
それに加えて、ご指定の住所まで車の引き取りも無料で可能。
ハイシャルへご連絡頂ければ、お電話口で愛車の査定額をお伝えします。


メーカーを選択してください
国産車
トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
スズキ
三菱
ダイハツ
いすゞ
光岡自動車
日野自動車
UDトラックス
輸入車
メルセデス・ベンツ
AMG
BMW
BMWアルピナ
アウディ
フォルクスワーゲン
オペル
ポルシェ
スマート
キャデラック
シボレー
ビュイック
ポンテアック
ハマー
GMC
フォード
リンカーン
クライスラー
ダッジ
ジープ
ロールスロイス
ベントレー
ジャガー
ランドローバー
ロータス
ローバー
ボルボ
サーブ
プジョー
ルノー
シトロエン
フィアット
アルファロメオ
フェラーリ
ランボルギーニ
マセラティ
ランチア
ヒュンダイ
その他・不明
車種を選択してください
走行距離を選択してください
10万キロ以上でも高価買取!
2万km未満
2万~4万km
4万~6万km
6万~8万km
8万~10万km
10万~15万km
15万~20万km
20万km以上
都道府県を選択してください
全国どこでもお引き取り無料!


メーカーを選択してください
国産車
トヨタ
レクサス
日産
ホンダ
マツダ
スズキ
三菱
ダイハツ
いすゞ
光岡自動車
日野自動車
UDトラックス
輸入車
メルセデス・ベンツ
AMG
BMW
BMWアルピナ
アウディ
フォルクスワーゲン
オペル
ポルシェ
スマート
キャデラック
シボレー
ビュイック
ポンテアック
ハマー
GMC
フォード
リンカーン
クライスラー
ダッジ
ジープ
ロールスロイス
ベントレー
ジャガー
ランドローバー
ロータス
ローバー
ボルボ
サーブ
プジョー
ルノー
シトロエン
フィアット
アルファロメオ
フェラーリ
ランボルギーニ
マセラティ
ランチア
ヒュンダイ
その他・不明
車種を選択してください
走行距離を選択してください
10万キロ以上でも高価買取!
2万km未満
2万~4万km
4万~6万km
6万~8万km
8万~10万km
10万~15万km
15万~20万km
20万km以上
都道府県を選択してください
全国どこでもお引き取り無料!
普通車は約13年、軽自動車は15年以上が平均寿命
車の寿命は、年数や走行距離だけで判断できるものではありません。というのも、車種や設計の違いによって使用できる期間が明確に異なるからです。
特に普通車と軽自動車では、平均寿命に2年以上の差が出ることがわかっています。
また、混同しやすいのが法定耐用年数という税金上の基準です。これは減価償却に使われるもので、実際の使用可能年数とは別物です。
この章では、普通車と軽自動車の平均寿命の違いや、法定耐用年数との関係について、初心者にも理解できるように丁寧に解説していきます。
普通乗用車の平均寿命は13〜14年
普通乗用車の平均寿命は13〜14年とされています。これは国土交通省所管の自動車検査登録情報協会が発表している統計で、車が廃車になるまでの平均使用年数を示しています。
新車購入から約7回の車検(=14年前後)を経た頃に、多くの人が買い替えや廃車を選ぶのが一般的です。
一方で、税制上の法定耐用年数は6年とされていますが、これはあくまで会計処理や減価償却のための指標です。実際の使用可能年数とは必ずしも一致しません。そこで、法的な数値と実際の平均寿命の違いを明確に把握できるよう、以下にまとめました。
- 法定耐用年数:6年
- 実際の平均寿命:約13~14年
上記のように、税法で定められた数字ではなく、車の実際の状態に目を向けることが重要です。
たとえば、エンジンの始動音がスムーズかどうか、加速時に異音がしないか、整備記録がしっかり残っているかなど、日常的に確認できるポイントがいくつもあります。
寿命を「見た目の年数」や「走行距離」だけで判断すると、まだ使える車を早期に手放してしまうことにもなりかねません。数字だけに頼らず、状態をしっかり見極める目を持つことで、車をより長く、安全に使うことができます。
次は、軽自動車の寿命について、普通車との違いやその背景を詳しく見ていきましょう。
軽自動車は15年以上使えるケースも
軽自動車は、車体がコンパクトで部品が軽いため、エンジンや足回りへの負荷が小さい設計になっています。その結果として、普通車よりも寿命が長くなる傾向があります。
軽自動車検査協会の統計によると、軽自動車の平均使用年数は15年以上に伸びており、この数値は年々更新されています。さらに、排気量が660ccに制限されていることで燃費性能が高く、税金や保険料も抑えられるため、家計への負担が少ないのも魅力です。
近年では、衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報などの安全装備も標準搭載されるようになり、安心して長く乗れるモデルが増加中です。こうした性能とコスト面のバランスの良さが、軽自動車の人気を支えています。
令和5年(軽自動車は令和4年)の軽自動車の法定耐用年数と使用年数の比較です。
- 法定耐用年数:4年
- 軽自動車(乗用):15.83年
参考:一般財団法人自動車検査登録情報協会、軽自動車検査協会
このような理由を踏まえると、「軽自動車はすぐ壊れる」という印象は、過去のものです。実際には、日常の点検や部品交換を欠かさず行っていれば、20年以上走る軽自動車も存在します。
寿命が伸びた原因は、各自動車メーカーの技術力のアップにより、自動車自体の耐久性が向上したのが大きな理由といえます。
このようなデータを参考にして、車を購入してから廃車にするまでの期間は、派手な事故で大きなダメージを受けない限り、13〜15年が目安と考えていいでしょう。

寿命の目安は走行距離10〜30万km
車の寿命を考えるとき、年数と同じくらい大切なのが「走行距離」です。
一般的な乗用車の場合、寿命の目安は13万km前後とされています。これは、平均的な使用年数(約13年)と年間走行距離(1万km)をもとにした目安です。ただし、整備状況や使用環境によっては20万km以上走ることもあります。
走行距離が増えるにつれて、車の中のパーツはどうしても少しずつ劣化していきます。
特に「10万km」「13万km」「30万km」といった節目では、それぞれ気をつけたいポイントが変わってきます。
車を長く安心して使うためにも、以下のような違いを知っておくと安心です。
| 距離の目安 | 主なトラブル | 必要な対応例 |
|---|---|---|
| 10万km | タイミングベルト・バッテリー | 定期交換でトラブル予防 |
| 13万km | 足回り部品の劣化・エンジン不調 | ショックアブソーバーや点火系の点検 |
| 30万km | オーバーホールの検討 | エンジン・ミッション全体の点検 |
走行距離が増えるにつれて、車にはそれぞれの距離に応じたトラブルが出やすくなります。
たとえば10万km前後では、タイミングベルトの劣化やラジエーターの冷却機能低下といった消耗系トラブルが増えてきます。13万kmを超えると、エンジンからの異音やハンドル操作時の違和感といった走行性能に関わる不具合が目立ちはじめ、30万kmともなれば、エンジンの圧縮不良やオイル漏れなど本格的な劣化が進むこともあります。
もし、「最近エンジン音が大きくなった」「発進時にカタつく感じがする」「ブレーキが効きにくい」といった症状が出ているなら、それは車からのサインかもしれません。
早めに点検し、必要な部品を交換することで、大きな故障を未然に防げます。
長く安心して乗り続けたいなら、距離の節目ごとに予防整備を行うことが大切です。
とくに10万kmを迎える前には、タイミングベルト、ウォーターポンプ、バッテリー、ブレーキパッドなどの消耗部品をチェックしておくと安心です。
それぞれの部品は走行性能に直結しているため、不具合を放置すると大きな事故や修理費用につながるおそれがあります
次の章では、年数や距離とはまた違った視点である「税金による寿命の区切り」についてお話しします。13年目・18年目に待っている増税と、そのタイミングが買い替え判断にどう関わってくるのかを詳しく解説します。
13年・18年目で増税されるので注意
車を長く乗り続けていると、「気づかないうちに税金が高くなっていた」というケースがあります。
その原因は、自動車税や自動車重量税に課される重課税制度にあります。これは、古い車ほど環境に負荷をかけやすいという理由から、登録から13年・18年が経過した車両に対して税金が加算される仕組みです。
特にディーゼル車は重課税の対象時期がガソリン車より早く11年目からとなっており、注意が必要です。
こうした制度はユーザーの維持費負担をじわじわと増やす要因にもなっています。
以下に車の種類ごとにいつから、どのくらい税金が上がるのかを分かりやすくまとめています。
▼自家用車、LPガス車、ガソリン車(ハイブリッド車以外)の自動車税(2019年9月30日以前に新車登録をした車)
| 排気量 | 新規登録から 13年未満 | 新規登録から 13年以上 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 約33,900円 |
| 1,000cc超~1,500cc | 34,500円 | 約39,600円 |
| 1,500cc超~2,000cc | 39,500円 | 約45,400円 |
| 2,000cc超~2,500cc | 45,000円 | 約51,700円 |
| 2,500cc超~3,000cc | 51,000円 | 約58,600円 |
| 3,000cc超~3,500cc | 58,000円 | 約66,700円 |
| 3,500cc超~4,000cc | 66,500円 | 約76,400円 |
| 4,000cc超~4,500cc | 76,500円 | 約87,900円 |
| 4,500cc超~6,000cc | 88,000円 | 約101,200円 |
| 6,000cc超 | 111,000円 | 約127,600円 |
参考:総務省
▼軽自動車税(令和5年度現在)
| 初度検査年月 | 新規登録から 13年未満 | 新規登録から 13年以上 |
|---|---|---|
| 平成27年3月31日以前 | 7,200円 | 12,900円 |
| 平成27年4月1日以降 | 10,800円 | 12,900円 |
参考:総務省
このように、13年以上経過すると自動車税は15%、軽自動車税は20%アップします。
また、車の重量に対して課税対象となる自動車重量税も車の新規登録をしてから年月が経過すると、増加する仕組みです。増加の割合を以下の表にまとめました。
▼自動車重量税
| 車両重量 | 新規登録から 13年未満 | 13年〜18年未満 | 18年以上 |
| 0.5トン以下 | 4,100円 | 5,700円 | 6,300円 |
|---|---|---|---|
| ~1トン | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| ~1.5トン | 12,300円 | 17,100円 | 18,900円 |
| ~2トン | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| ~2.5トン | 20,500円 | 28,500円 | 31,500円 |
| ~3トン | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
参考:国土交通省
このように税金の上昇は徐々に進んでいき、13・18年目で突然価格があがって驚く人も少なくありません。とくに13年目や18年目は、重課税に加え、年式に伴う修理や交換部品の増加で維持費が一気にかさみやすい時期です。
「まだ走れるから大丈夫」と思っていても、実際には燃費の悪化や補修コストの増加、税金の上昇などが重なり、結果的に新車や高年式中古車へ乗り換えた方が割安になるケースもあります。
もちろん、長く乗ってきた愛車への愛着は大切です。ただし、冷静に費用対効果とライフスタイルの変化を見つめ直すタイミングとして、13年・18年目はひとつの区切りになるでしょう。
次の章では、年数や税金の条件に左右されずに車をできるだけ長く使うために、日々できるメンテナンスの工夫や運転のコツを具体的にご紹介していきます。愛車を少しでも長く使いたいと考えている方は、確認しておきましょう。
より詳しい内容を知りたい方は、13年・18年超の自動車税・重量税が一瞬でわかる早見表をご参照ください。
「走行距離と年数的にもまだ乗れるから車検手続きをしたいけど、店舗に行くのが少し面倒・・・」
そんな方におすすめなのが、スマホで車検証をアップロードするだけで見積もり金額が分かる【モビフル車検】です。
主要部位の整備費用、代車代金すべて含まれているので、車検後に想定外の金額になる心配がなく安心です。
車の寿命を20年まで延ばすには日々のケアが重要
維持費や税金がかかっても、愛着のある車は手放したくないという人もいるでしょう。
そのような人のために、車に乗り続けるための2つのコツを紹介します。
▼車の寿命を延ばす2つのコツ
- オイル交換や空気圧チェックを定期的に行う
- 急発進・急ブレーキに注意する
上記のコツを意識して乗れば、車の寿命を20年にまで伸ばすこともできます。
オイル交換や空気圧チェックを定期的に行う
車の寿命を20年以上に延ばすためには、適切なメンテナンスと負担の少ない運転習慣が欠かせません。
実際、日本自動車工業会によると、平均車齢(車の使用年数)は年々上昇傾向にあり、乗用車では10年を超える水準となっています。これは、車の品質向上だけでなく、ユーザーのメンテナンス意識の高まりによるものです。
車の不調は必ずしも目に見えるわけではなく、内部の部品は走行距離に応じて確実に劣化していきます。だからこそ「壊れてから対処」ではなく、「壊れる前に備える」ことが重要なのです。
以下に、特に重要な日常点検の基本項目とその目安をまとめています。車を長持ちさせたい方は、これらの目安を習慣化することから始めましょう。
| 点検項目 | 推奨タイミング | 寿命・交換目安 |
|---|---|---|
| エンジンオイル | 5,000〜10,000kmごと | 半年〜1年ごと |
| オイルフィルター | オイル交換2回に1回 | 1年ごと |
| タイヤ空気圧 | 月1回チェック | 数値異常なら即対応 |
| クーラント(冷却水) | 2年に1回 | 劣化・減少に注意 |
上記に挙げた点検項目は、どれも安全に直結する要素ばかりです。
たとえばエンジンオイルは、金属部品の摩擦を抑えてエンジンをスムーズに動かす重要な役割を担っています。劣化したオイルを使い続けると、燃費の悪化やエンジンの故障を招くだけでなく、最悪の場合、高額な修理費用がかかるリスクも。
タイヤの空気圧に関しても、低下したままだと接地面が不安定になり、ブレーキ性能の低下や事故の原因になることもあります。
こうした消耗品は、数分のチェックと少額の交換費用で、大きなトラブルを未然に防げる「費用対効果の高い予防策」と言えるでしょう。
忙しい日々の中でも、月に一度は点検する習慣をつけることが、車を長く乗るうえでの第一歩となります。
急発進・急ブレーキを避ける運転を意識する
車を長く使い続けるためには、日々のメンテナンスとあわせて運転のしかたを見直すことが非常に重要です。特に、急発進や急ブレーキといった荒い操作は、車の各部品に過度な負担をかけ、結果として摩耗や故障を早める原因となります。
たとえば急ブレーキはブレーキパッドを早くすり減らし、サスペンションには一気に大きな衝撃がかかるため、足回りの不具合を引き起こしやすくなります。
また、タイヤも一部に偏った負荷がかかることで寿命が縮み、パンクのリスクが高まります。こうした影響はすぐには表れないものの、蓄積されることで数年後に思わぬ修理費用となって跳ね返ってくることがあります。
つまり、日々の運転動作そのものが、車の将来の状態を大きく左右するということです。
以下は負荷を減らす運転のポイントです。
- ゆっくり発進し、一定速度を保つリスト
- 早めのブレーキで衝撃を抑える
- 坂道ではアクセルとブレーキの操作を丁寧に
- カーブでは減速を意識する
これらの運転ポイントを意識するだけでも、車の構造部品にかかるストレスは大幅に軽減できます。
たとえば、ゆるやかな加速と減速を習慣化することで、ブレーキ系統の寿命を数千キロ単位で延ばせるケースも報告されています。また、サスペンションの劣化が抑えられれば、乗り心地や走行安定性も維持されるため、安全性の面でも大きなメリットがあります。
さらに、無理のない運転は燃費の改善にもつながり、トータルでの維持費を抑える効果も期待できます。車は消耗品の塊ですが、その劣化スピードは乗り方次第で確実にコントロールできます。
日々の運転の積み重ねが、車の寿命と家計の負担に直結するという意識を持ち、今日から実践してみましょう。

部品交換の時期と費用の目安
車は走る機械である以上、部品は徐々に劣化していきます。特に寿命が短く、トラブルを起こしやすい消耗部品は注意が必要です。
交換時期を把握し、あらかじめ費用の目安を知っておくことで、急な出費を避けられます。この章では交換頻度が高く、費用も大きくなりがちな主要パーツとその交換コストの相場を紹介します。
あわせて長期使用で注意すべき純正部品の供給リスクについても見ていきます。
主要部品ごとの交換時期と費用目安
走行距離や経年劣化によって交換が必要となる部品は多く存在します。
自動車の部品は寿命が近づくと性能が急激に低下する傾向があり、突然のエンジントラブルや制動力の低下を招くリスクがあります。
深刻な故障を防ぐためにも、部品ごとの交換時期や費用の目安を把握し、適切なタイミングでメンテナンスを実施することが、車の寿命延長と安全維持のカギとなります。
主な部品とその交換タイミング、費用目安は以下の通りです。
| 部品の名称 | 交換の目安 | 費用 |
| エンジンオイル | 5,000km または6ヶ月 | 4,000円〜 |
| バッテリー | 3~5年 | 1万円〜 |
| エンジンオイルフィルター | 1万kmまたは オイル交換 2回ごと | 2,000円〜 |
| エアクリーナーエレメント | 2~3万km | 3,000円〜 |
| スパークプラグ | 2~3万km | 5,000円〜 |
| ラジエーター液(冷却水) | 車検ごと | 5,000円〜 |
| ファンベルト | 4万km | 6,000円〜 |
| タイヤ | 4~5年または 溝1.6mm以下 | 4万円 |
| タイヤ(ローテーション) | 5,000km | 2,000円 |
| ブレーキフルード | 車検ごと または2万km | 5,000円〜 |
| ブレーキシュー | 5~10万km | 1万5,000円〜 |
| ブレーキパッド | 3~4万km※ | 1万5,000円〜 |
| ドライブシャフトダストブーツ | 7~8万km | 3万円〜 |
| ヘッドライト | 通常の明るさ の70%以下 | 2,500円〜 |
| ワイパーゴム | 1年 | 2,000円〜 |
| エアコンフィルター | 1万km または1年 | 2,000円〜 |
| ウィンドウォッシャー液 | 1ヶ月ごと | 〜1,000円 |
| ワイパーブレード | 2年 | 2,500円〜 |
| タイミングベルト | 10万km または10年 | 5万円 |
| ファンベルト | 5~10年 | 5,000円〜 |
| ラジエターホース | 10万km | 1万円〜 |
これらの部品は、使用環境や運転頻度によっても寿命が変動します。たとえば短距離運転を繰り返すとバッテリーへの負荷が大きくなり、早期劣化の原因になります。
また、通勤や買い物でブレーキを頻繁に使用する都市部のドライバーは、ブレーキパッドの摩耗が早まりやすい傾向にあります。
こうした特性を理解したうえで、車検や定期点検のタイミングで一括して交換するなど、メンテナンスを事前に計画しておくと、結果的にコスト削減にもつながります。
突然の出費を防ぎ、車をより長く快適に使うためには、交換目安を無視せずに計画的な管理を行うことが重要です。
純正部品の在庫切れに注意
車を長期間乗り続けたいと考える際に見落とされがちなのが、純正部品の供給終了というリスクです。
一般的に自動車メーカーは、製造終了から10年程度を目安に補修用部品の供給を縮小または終了するケースが多く、年数が経つごとに部品入手が難しくなっていきます。
国土交通省のガイドラインでは保有期間に応じた部品の供給確保が求められているものの、全車種が対象とは限りません。
特に生産台数の少ない車種や輸入車などは、交換部品の価格が高騰したり、修理が長期化するリスクがあります。場合によっては、部品が見つからないことで車検すら通らなくなる可能性もあるため、供給状況の確認は非常に重要です。
今後も長く乗り続けたい方は、以下の点に注意しましょう。
- 購入前に部品の流通状況を調査するリスト
- 部品取り車として使える同型車の有無を確認
- メーカーが長期供給保証をしているかチェック
これらを押さえておけば、「突然修理できない」といった事態を避けられます。次章では、寿命が近づいた車の扱いとして、廃車買取という選択肢について詳しく解説します。
寿命が近い車は廃車買取がおすすめ
車の寿命が近づいたと感じたら、まず検討したいのが廃車買取という選択肢です。長年乗り続けた車は、故障や不具合が増えるだけでなく、部品交換や車検、税金など維持費全体が高額になりがちです。
特にエンジンや駆動系などの修理が必要になった場合は、見積額が車両本体の価値を大きく上回ることも珍しくありません。
そんな時、ただ廃車にするのではなく、買取業者に依頼すれば「鉄くずとしての金属価値」や「パーツ取り車」としての需要により、思わぬ価格がつくこともあります。海外では日本車の中古パーツの需要が高く、特に軽自動車やトヨタ・ホンダなど人気メーカーの車は動かなくても価値がある場合もあります。
廃車のタイミングを誤らないよう、判断材料として以下のような基準をチェックしておきましょう。
- 修理見積が車両価値を大きく超えたとき
- 走行距離が20万kmを超え、故障の頻度が増えたとき
- 部品供給が終了し、修理対応が難しくなったとき
- 税金や保険料など、維持費が割高になったとき
これらの条件に当てはまる車を手放す際は、ただ処分するのではなく廃車買取サービスを活用することで、思わぬ収益につながる可能性があります。
では、廃車買取を検討するときにどのようなところを選べばよいかについて、以下も確認しておきましょう。
| 比較項目 | ディーラー | 中古車販売店 | 廃車買取店 |
|---|---|---|---|
| 出張査定 | △ (基本店舗持ち込み) | ◎ | ◎ |
| 現金での還元 | × | ◎ | ◎ |
| 不動車や事故車の 買取 | × | × | ◎ |
レッカー代・抹消登録・解体費用などが無料の業者も多く、完全に動かなくなった車でも引き取り対象となるケースがあります。
特に「車検切れ」「エンジン不動」「放置車両」など状態が悪い車でもOKという業者を選べば、手間も費用もかけずに処分が可能です。
ハイシャルでは、年式10年以上・走行距離10万キロ以上の車でも買取を行っています。
ハイシャルには、以下3つの利点があります。
- 0円以上の買取価格を保証
- 事故車や故障車でも対応
- 面倒な廃車手続きを無料で代行
ハイシャルは全国の車の解体工場やオークション会場など、多様な販路と提携しており、お客様のお車の価値を最大限に引き出すための最適な選択が可能です。
詳しくは、ホームページや以下の記事もご覧ください。

まとめ
車の寿命は、年数で見ると13〜15年、走行距離では13万kmが一つの目安とされています。ただし、これはあくまで統計上の平均値に過ぎません。現実には、整備の頻度や走行環境、運転スタイルといった要素によって寿命は大きく変動します。たとえば、きちんとオイル交換を行い、無理のない運転を心がけている車は、20年以上、走行距離30万km超でも問題なく使用されている例が多くあります。
本記事では、そうした実例やデータに基づき、車をできるだけ長く使い、寿命による買い替えや急な故障による出費を防ぐために押さえておくべきポイントを詳しく解説してきました。その内容を、最後に以下に整理しておきます。
- 普通車の平均寿命は13〜14年、軽自動車はそれ以上も可リスト
- 10万km超から不具合が増えるが、30万km超えも可能
- 13年・18年で税金が上がるため、その前に買い替え検討も
- オイル交換や空気圧チェックなどの基本メンテが重要
車は単なる移動手段ではなく、長期的に見れば大きな資産でもあります。だからこそ、ただ買う・乗るだけでなく、「どう管理するか」「いつ手放すか」といった判断が、家計にも安全性にも大きな影響を与えます。