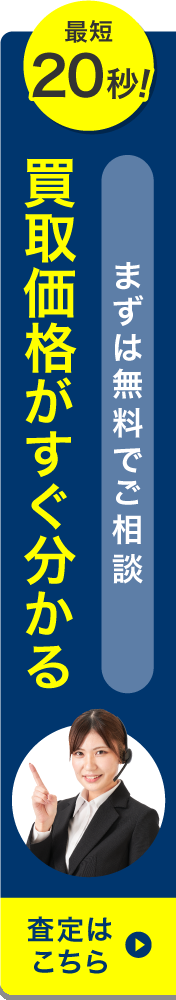廃車を代行できる業者はこの3つ!手続きの流れやお得に手放すポイントも紹介

カーネクストが悪質と言われる4つの理由!実際の評判と口コミを調査

事故車はディーラーで下取り可能?減額されやすい理由と2つの注意点を解説

カーネクストは店舗がない?買取の流れやからくりを解説

下取車手続代行費用とは?下取りの手数料や費用の相場をケース別に解説

ディーゼル車の自動車税は11年目に15%あがる!排気量別の税金額まとめ

【保存版】所有権解除とは?やり方・費用・必要書類を徹底解説!

雹(ひょう)害車は査定でいくら減額される?実際の買取事例も紹介

雹(ひょう)の被害で車がボコボコに!全損の場合に車両保険は使える?

雹(ひょう)やあられによる車の凹み・傷の修理費用が丸わかり!デントリペアで直る?

【パーツ別】車の修理費用の相場一覧!事故車はいくらで直せる?

軽自動車のエンジン交換費用は30万円?載せ替えを安くする3つのコツ